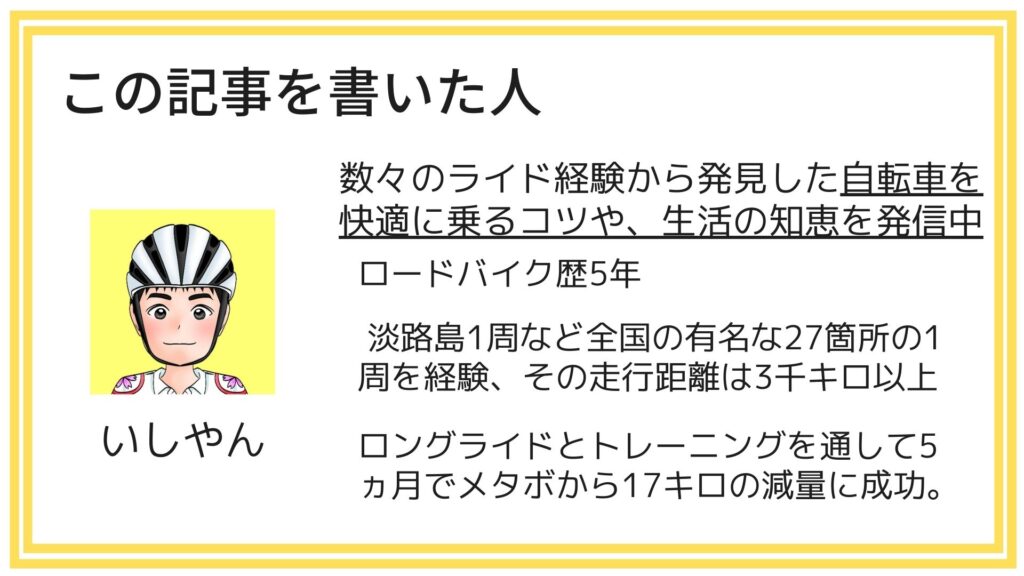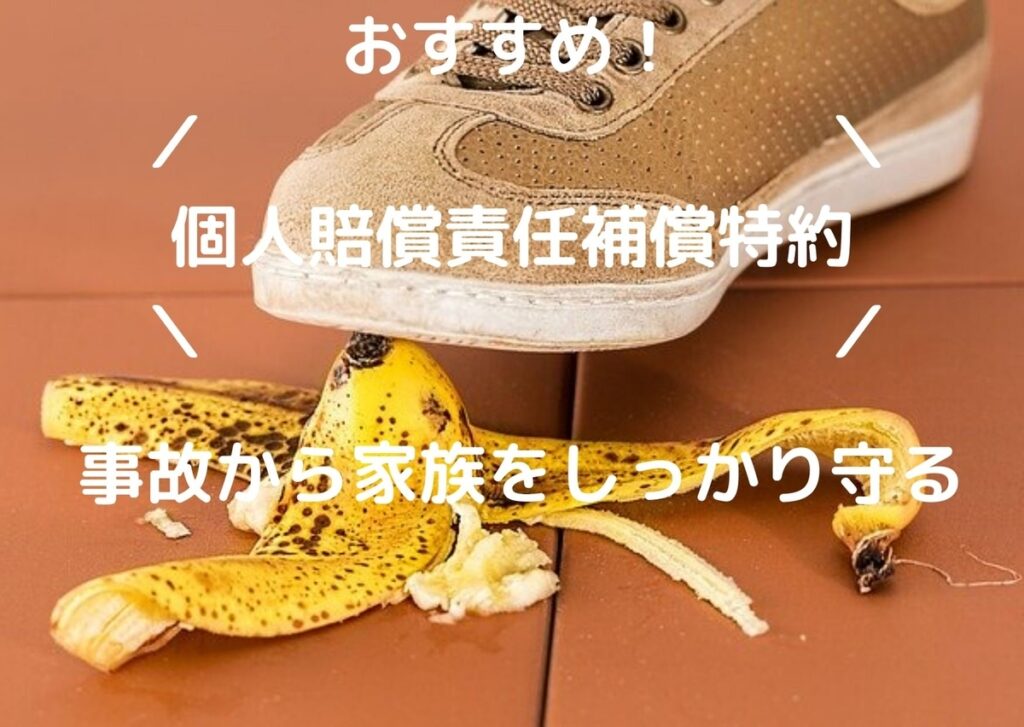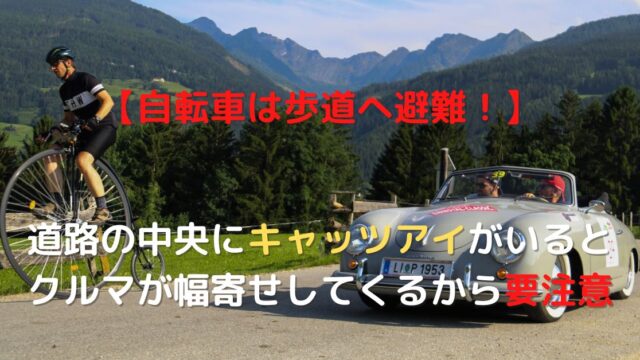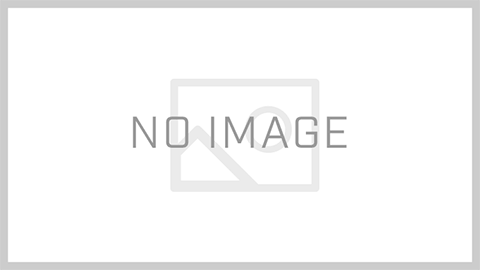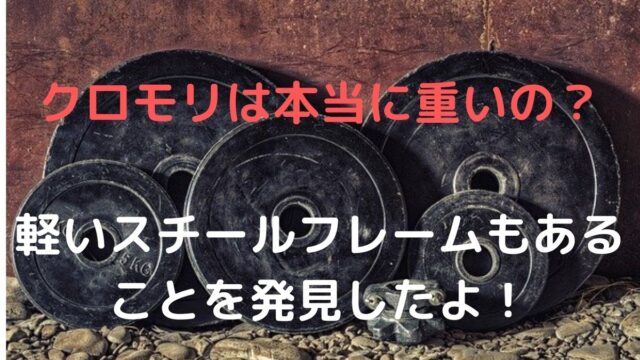【防犯登録を必ず行う理由】警察による突然の職務質問で慌てない為に
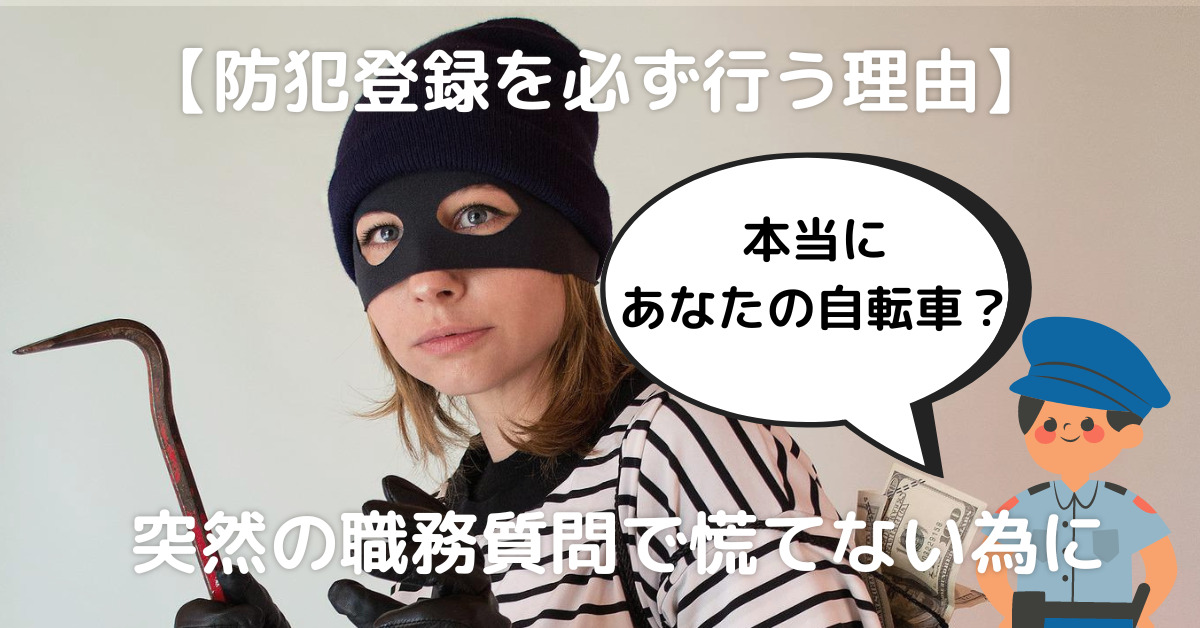
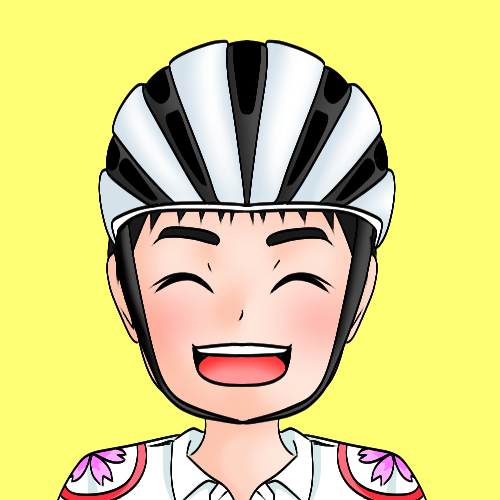
自転車の防犯登録は行ってますか?
今日の記事では、防犯登録をしておかないと、警察に窃盗犯に間違われる可能性があることを書きたいと思います。先日、ロードバイクで走っていると、警察から職務質問を受けました。職務質問を受けるのは生まれて初めてです。
その中で、ロードバイクの防犯登録のことを問われました。
最近は、自転車の盗難被害が最近多いので積極的に呼び止めているとのことです。つまり自分は犯人と疑われたのでした。防犯登録をすることは自転車に乗る人の義務です。しかし、反則金が課せられないので登録をしてない人が多いようです。
とは言っても、防犯登録をしてないと急に確認されたときに自分の自転車と証明できず、犯人と疑われることがわかりました。職務質問などで、疑われてしまったらすぐに帰れないかもしれませんし、疑いを解くのに時間がかかるかもしれません。
今日の記事では、そんな防犯登録の登録方法について書きたいと思います。この記事にり防犯登録が広まり、安心して自転車に乗ってもらえるようになるとうれしいです。
自転車の防犯登録は国民の義務

自転車の防犯登録は、車種を問わず義務となってます。しかし、登録してないからと言って罰則はありません。法律で以下のようにしっかりと定められています。
第十二条の3
引用:「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」
自転車を利用する者は、その利用する自転車について、国家公安委員会規則で定めるところにより都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録(以下「防犯登録」という。)を受けなければならない。
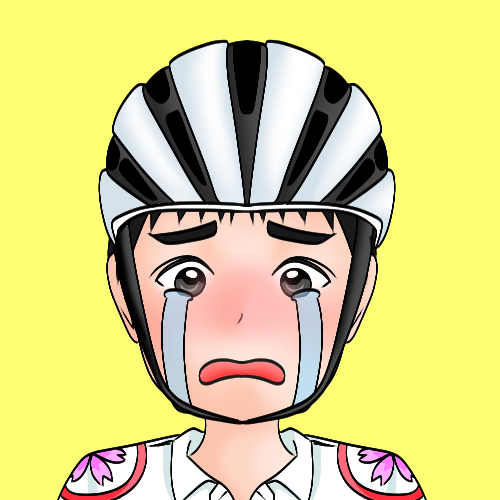
反則金等のペナルティがないので、
義務化されても防犯登録してない人も多いです。
しかし、自転車が無くなった時などは防犯登録の情報を元に探します。自転車保険は、防犯登録してある自転車しか取り扱いません。
また、所有者の確認は日常でも行われるので、あらぬ疑いを掛けられるまえに防犯登録を速やかに行いましょう。
防犯登録の登録方法について
防犯登録は、警察ではできません。指定業者を通して防犯登録を行うようになっています。
指定事業社は多くの自転車販売店が指定されてるので、購入元の自転車店やWEBショップに確認をしましょう。
登録には、登録量が若干かかります。愛知県の場合は600円です。これは都道府県により異なりますが似たような金額です。
防犯登録するタイミングは、店舗で自転車を購入すると同時に済ませるのが手間がなくて良いです。
以下は私の実際の登録証です。登録証の形は各自治体により異なります。現在の防犯登録証にはQRコードが付いており、警察の方はこれをスキャンすることによって瞬時に所有者を確認します。


後から登録は面倒なので、買ったと同時が手間が一番少ないよ
防犯登録の目的

防犯登録の目的は所有者を明確にするためです。かつて違法な放置自転車が急増したことで防犯登録の制度が制定されました。
自転車防犯登録制度は、昭和55年(1980年)に成立しました。そして、平成6年(1994年)に改正が行われ、防犯登録は義務化されました。
当時は、駅前など多くの自転車が放置されるようになってきたのです。放置自転車が増えることで、歩行者や商業施設等の通行や活動の妨げとなりはじめました。
放置自転車の何割かは盗難自転車だったりので、誰も引き取らず放置され社会問題化しました。
そこで、防犯登録を義務化することにしたのです。
防犯登録を行うことで所有者が明確になります。明確にすることで、もし自転車が無くなっても、速やかに持ち主に返せる仕組みを作ったのです。その結果、防犯登録制度が放置自転車の減少に貢献しました。
防犯登録の目的をまとめると次の3つとなります。
- 持ち主の明確化
- 放置自転車の削減
- もし無くしても速やかに持ち主の元に戻ってくる可能性を大きくする
背景を知ると、防犯登録は社会貢献にも役立ち、登録者にもメリットがあるのでまだの方はなるべく速く登録をしましょう。もし、盗難にあっても愛車が戻ってくる可能性が高まります。
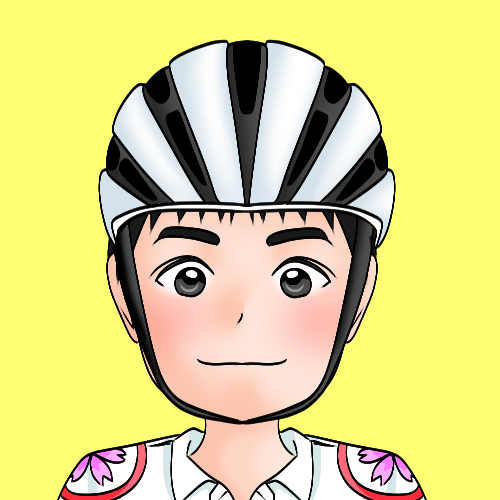
何も書いてなかったら、誰のか全くわからないものね!
防犯登録は自分のためになるよ。
防犯登録と合わせて自転車保険に入ることも良い選択
ロードバイクのような高額な自転車は自転車保険に入ることも検討しましょう。
警察の話によると、昔は自転車が盗まれても発見されるケースは比較的多かったようです。盗まれる自転車は、「ちょっとそこまでの足がわり」として使われることが多かった為です。
乗り捨てられることがほとんどだったので発見されて持ち主にまで返ることが多かったようでした。
しかし最近は違います。
ロードバイクが盗難されるとほぼ見つからないようです。その理由は、ネットオークション等で売られてしまうからです。
こういった事情があるので、防犯登録と一緒に、自転車の保険に加入することを強くお勧めします。自転車の保険には大切な自転車が無くなった時、次の自転車の購入サポートが受けられものがあります。
自転車保険は、車両の盗難に限ったものではなく、事故の被害者や加害者になった時の損害賠償をサポートするものもあります。自転車保険については以下の記事でまとめましたのでよろしければご覧ください。
忘れず自転車保険の更新はしてますか?忘れると大変!何も起きないから大丈夫と思わずに更新はお忘れなく|いつ何時何が起きるかわからない
特に損害賠償については、1億円に迫るケースもあります。そのため、学校や企業では防犯登録を必須とするケースが増えてます。各自治体でも条例レベルでも義務化しているところが増えてきてます。
事故のケガに対する備え、物損に対する備えを自転車保険でカバーすると安心してロードバイクを楽しめますね。
盗難、紛失以外でも使われる防犯登録の情報

実際に職務質問された私ですが、なぜ職務質問されたかというと、自転車盗難が増えているというのは建前で、実はとても怪しく見えたのかもしれません。
人も車もまばらな深夜の田舎道をサイクルジャージを着て走ってました。きっと相当怪しかったのでしょう。
職務質問の中で、防犯登録の有無を問われました。警察はその場で、登録証をスキャンして利用者照合を行いました。
もし、防犯登録してない場合、自分の自転車が盗難車でないことをその場で証明しなければなりません。
無事に証明できて良かったです。
防犯登録はとても大事ですが、極力自分の自転車に乗るということも大事ですね。自転車を借りて出かける時は職務質問のことも考えておくべきでしょう。
事故と盗難から自分を守るため、防犯登録・自転車保険加入を行いましょう
今日の記事では自転車に乗る人にとって、防犯登録と自転車保険を準備しておかないと、事件が起きた時に何の手も打てなくなります。記事の要点は3つにまとまります。
- 防犯登録は速やかに行う — 自転車が紛失時に見つかる可能性アップ
- 自転車保険も加入する — 代替品購入や損害賠償のサポートが受けられる
- 自分の自転車以外に極力乗らない — 照合されたとき盗難車に疑われる
防犯登録と自転車保険の準備をして、安心して自転車に乗りたいですね。
自分自身と家族を事故からしっかり守ることをお忘れなく
ロードバイクの事故に備えるときは「個人賠償責任補償特約」もチェックしよう。莫大な賠償金から家族をしっかり守れます